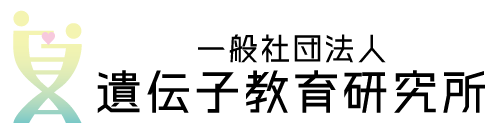○ 7月 尚次郎の子育てコラム
さて、今回は、「夫婦の会話や生活経験と子どもの知能」というお話をしたいと思います。
子どもの知能の発達に、夫婦や家族の会話も重要です。
特に、赤ちゃんのうちは、夫婦の会話を聞いていないようで、実はしっかりと聞いているものです。
もちろんその意味はよくわかっていなくても、なんとなくでもその会話の内容を聞いているのです。
特に、楽しそうにしている会話は、その雰囲気から、赤ちゃんは感じ取っているのです。
夫婦や家族の会話が豊かであれば、自然と親子の会話も豊かなものになります。
会話に出てくる言葉は、子どもの知能の発達にも大きな影響を与えます。
夫婦や家族の会話が豊かな家庭で育った子どもを追跡調査したところ、大学進学率が高く、優秀な成績だったというデータもあるほどです。
また、幼いころの生活経験は、子どもの知能やことばの発達には、欠かせないものです。
家族でどこかに出かける経験は、その後のその子どもの人生に(知能発達に)大きな影響を与えます。
幼いころから、列車に乗っていろいろな場所にいっている子どもは、社会科の地理や歴史にも興味をもつとも言われます。
また、そこで経験したこと(見たこと、聞いたこと、したことなど)は、子どもの知能だけでなく、豊かな情操も養うのです。
また、いっしょにお買い物にいくのも、立派な経験です。
お買い物は日常生活の中の一コマでしょう。
そこでことばや知能を発達させる経験の機会はたくさんあります。
お買い物の途中で、公園でうぐいすの鳴き声がしはじめたら
「もうすぐ春ね。」
セミの鳴き声やひまわりの花をみたら、
「もうすぐ夏がやってくるね。」
など、子どもの話しかけてあげて下さい。
また、公園の花がしおれていたら
「お花さんたち、お水がほしかったんだろうね。さぞのどがかわいたことでしょうね。」
と、動植物を擬人化して、話しかけてみるのもよいでしょう。
幼稚園から小学校低学年の子どもは、アニミズムの世界に生きています。
つまり、動物や植物、または命のないものでも、すべてに命を宿したり、動物や植物を人に見立てて、その気持ちを悟ったしていくのです。
そのような経験が、生命への畏敬の念になっていくのです。
子どもたちは生活経験の中で、言葉の意味を学び、語彙を増やしたり、自分の思い通りにならなかった経験から、思考力や忍耐力も育んでいくのです。
有名、私立小学校の入学試験では、そのような生活の一場面の絵を提示し、その絵から連想されることや、登場人物の気持ちを聞く試験があります。
一枚の生活場面の絵から、さまざまな状況や心情を推測していく力が問われるのです。
これは、さまざまな生活経験をしていなければ、なかなか推測できないものです。
生活経験は、写真や絵だけを見て得た知識とは違うのです。
つまり単なる情報の理解でなく、人の気持ちといった感受性も育むことができるのです。
最近、ゲームなどのバーチャルの世界に生きる子どもが増えています。
知識豊富な頭でっかちな子どもが多く、人の気持ちを理解することが苦手な子どもが多いのです。
夫婦の会話や生活経験は、子どものことばの力を伸ばすだけでなく、感情をも育んでいくことになるのです。
<遺伝子にまつわる今日のひとこと>
今回は、「遺伝子BDNF」についての一言です。
BDNF(脳由来神経伝達因子)は、脳内のシナプスのつながりに関する遺伝子です。
能力遺伝子検査でも、このBDNFの状態を見るものもあり、主に「記憶の傾向」を鑑定しています。
今回はGG型です。GG型は記憶が得意とされ「堅実家タイプ」といわれます。
GG型は、記憶することについては得意な方で、コツコツと意味やわけを確認しながら覚えていこうとします。
ノートや練習帳などでの書き込みなどはきちんとこなし、それにより憶えていくことができますし、記憶はよい方です。
ただ、自分が記憶していないことや自信がないことについては、テストにおいてもなかなか出てこない傾向もあります。やはり同じ問題でも、数回繰り返ししていくことで記憶に対する自信をもち、テストなどの答えを出していけるようになります。
こつこつ憶えていくことを好みますから、しっかりと意味やわけ、またはそのメカニズムなどを理解した上での「反復練習」や「学習方法」が適しているといえるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
尚次郎